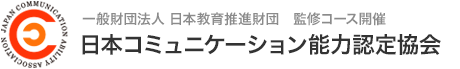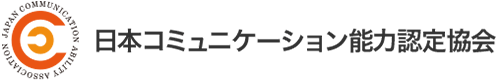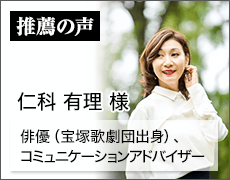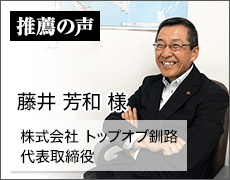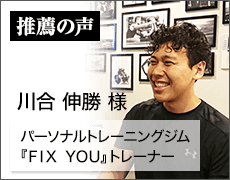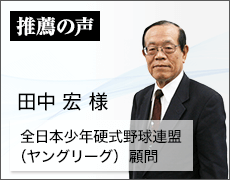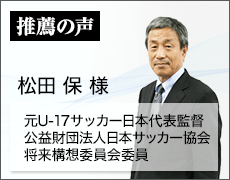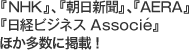わかりあえないことから ─ コミュニケーション能力とは何か
わかりあうのは難しい。
だからこそ、コミュニケーションが必要。
そう再確認し、学びを深めたいと興味のわく1冊です。
「コミュニケーション」の問題というのは、結局のところ
「わかりあう方法や、他者との違いを知ること」が欠けている
のではないでしょうか。
協会宛に、社員のコミュニケーション能力を高めたい、
という研修依頼やご相談をよくいただきます。
どんなことが起きているのかを伺うと、
「若い社員が積極的に発言をしない」
「何を考えているのかわからない」
「我々の常識では考えられない言動がある」
こんな風に、担当の方すら明確に表現するのが難しいようで、
ではどのように改善していきたいか?という点もあいまいだったり...。
"何となく起こっている" 社内の違和感や問題を総称して
「コミュニケーション」の問題と捉えているように感じます。
以下、著書から
* * *
・・・工業立国においては「ネジを90度曲げなさい」と言われたら
90度曲げる正確性とその能力が求められてきた。
しかし、付加価値(人との違い)が利潤を生むサービス業中心の社会においては、
90度曲げる能力、いわゆる従来の基礎学力に加えて、60度曲げてみよう
という発想や勇気、あるいは「120度曲げてみました、なぜなら・・・」と
説明できる表現力やコミュニケーション能力がより重視される。
* * *
より多様性や柔軟性の高いコミュニケーションが求められる時代になったけれど、
その変化、多様化の途上で悩む企業も多いのかもしれません。
コミュニケーション能力をなぜ高めるのか?
違いを知ること、違いを埋めることが、
信頼関係をつくる一歩だからなのでしょう。
基礎を学んだ方にもぜひ読んでいただきたい1冊です!