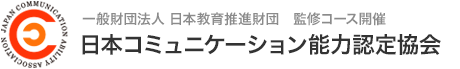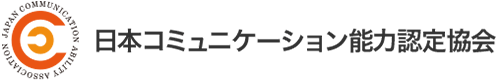推薦の声 古木 祥子様 株式会社アクティング Growing facilitator(グローイングファシリテーター) - コミュニケーション資格講座・検定|コミュニケーション能力認定協会
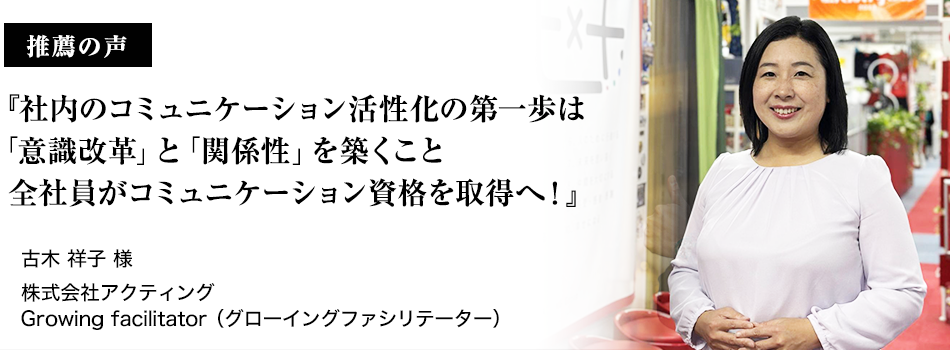
社内やチームのコミュニケーションをもっと活性化させたい、
とお考えのリーダーや管理職の方は多いのではないでしょうか。
一方で、なかなかそれが実現しないというお声もたくさんあります。
今回お話をお伺いした古木祥子さんは、人材育成担当としてトレーナーの資格を取得。
全社員にコミュニケーション能力認定講座を導入し、研修事業の新規展開も推進されています。
古木さんご自身も、コミュニケーションの講座を受講することで、
周囲との関わり方に大きな変化を経験したとおっしゃいます。
受講による変化や、風通しの良い社内環境を作るためのコミュニケーションの取り組みをお伺いしました。
<プロフィール>
2009年入社。プロ野球やプロサッカーの試合、コンサートなど、イベント運営の請負事業に従事した後、2019年から人材育成担当として新入社員研修や社員教育を担当する。コミュニケーション能力認定講座を全社員に導入し、研修事業の新規展開を推進する。
当たり前のことに気づかず、いつの間にか壁を作ることに
― コミュニケーション講座を受講するにあたって、古木さんご自身は、
コミュニケーションや人間関係に何かお悩みや課題がおありだったのですか?
実は、コミュニケーションやNLP(心理学)を学ぶまでは、
私はコミュニケーションに課題があるとは全く思っていませんでした。
弊社はもともと社内のコミュニケーションは良好だと感じており、
私自身も問題なくコミュニケーションが取れていると...。
ところが、「問題ない」と思っていたのは自分の思い込みであって、
そのせいで視野を狭めてしまっていたと、今では思います。
自分が当たり前と思っていることが、他の人にとっては当たり前ではない。
こんなにシンプルなことに、なぜ気づかなかったのかと、今では不思議に思うくらいです。
どういうことかと言いますと、
会社のメンバーとのコミュニケーションで食い違いが起こっても、私は正しいことを言っている、
当たり前のことを言っているのに、相手が理解できていないのだと思っていました。
理解できていない相手が悪いのだ、なぜ理解できないのだとイライラすることもありましたから、
周囲のメンバーは私のことを怖いと思っていたでしょうね。笑
特に年次の浅いメンバーとの間に、知らず知らず、壁ができてしまっていたように感じます。

▲社内でのコミュニケーション能力認定講座の開催。すでに100名以上が受講
― コミュニケーション講座を受講されたきっかけは、どのようなことだったのですか?
自分のコミュニケーションに問題がある、とは思っていませんでしたので、
当時はコミュニケーションを学ぼうとはまったく思っていませんでした。
それがある時、お取引のある企業の方から、NLPという心理学があると聞いて興味を持ったんです。
コミュニケーションを学ぶというより、自己成長のために、最初はNLPのコースを受講しました。
その後、関連団体の主催しているコミュニケーションの講座があることを知りました。
ちょうど私は社内で講師を始めた頃でして、
将来的には研修事業を展開できたらいいねという話も社内で出始めていました。
ですので、コミュニケーション講座を知った時にはトレーナー資格を取得することを決めていました。
「マインド」×「スキル」のバランスを重視
― コミュニケーションの講座は他にもたくさんありますが、
当協会の講座を受講された理由は何だったのでしょうか。
心理学(NLP)を取り入れた内容だったことです。
人間の深層心理を踏まえた上でのコミュニケーション、というカリキュラムが大きなポイントでした。
スキルだけでなく、人間関係を築く上での、根本になるマインドをしっかり学べることが重要でした。
「マインド」×「スキル」のバランスが大切だと考えていたからです。
こちらの講座は、まず人間教育の土台があって、コミュニケーションスキルがあるという考え方に共感しました。
コミュニケーションの根本がガラリと変わった
― 講座を受講していただいて、どのようなことが役立ちましたか?
たくさんありますが、まずは「観念のメガネ」です。
私にとって、コミュニケーションの根本を変えたと思います。
これまで私はよく「普通」と言っていたんですね。
どういうことかと言いますと、自分の仕事のやり方や、コミュニケーションの取り方が
「普通」だと信じていましたので、自分のできることは誰にでもできると思っていました。
ですから、自分ができて、他の人ができない時に、どうして「普通」のことができないのだろう...?と。
年次の浅いメンバーに対してもそのように思っていた部分があります。
ところが、「観念のメガネ」という、いわゆる「思い込み」があることを知ったんですね。
講座の実習で、その思い込みが原因でコミュニケーションがうまくいかないのだ、ということを突きつけられました。
今まで「普通」だと思っていたことが、
人によってはまったく違ったのだという、私にとっては大きな発見がありまして。
私には□に見えているものが、人によっては△に見えていることもある。
このくらいの大きな違いがあるのだなと...。
自分の視野を広げることになりましたし、
イライラしてしまうことが、本当になくなりました。
知っているかどうかで、人としての器を広げることもできる
他に「意識の5段階」や「自己重要感」を学んだことは、本当に大きなことだと感じています。
意識の5段階(人の意識は5つの階層に分けられるという考え方)のような捉え方なんて、
まずそんな世界があると知らないですよね。ここで勉強していなければ、多分私は一生知らずにいたと思います。
自己重要感を学んで、救われたと言う社員も多いです。
弊社はイベント運営時などに多くの方と接しますが、中には理不尽な物言いをされる方もいらっしゃいます。
これまでは、辛辣な言葉をそのまま受け止めて、落ち込むスタッフもいましたが、
その相手の心の中で何が起きているのか?
ということに意識を向けられるようになったら、心が楽になったと言ってくれます。
人の心を知ること、自己重要感のように大事なことを知っているだけで、
人との付き合い方や、相手を見る目が変わりますし、人としての器も広がるのだと思います。
新卒採用を機に、コミュニケーションの意識改革が必要に
― コミュニケーション教育にとても熱心に取り組まれていると感じますが、
御社内でコミュニケーション上の課題などはおありですか?
大きくは2つです。
1つ目は、世代間でのコミュニケーションに課題が出てくるようになりました。
弊社はアルバイトから社員になる人が多かったので、アルバイト期間中に社員との関係性が作られていました。
2018年から新卒採用をスタートし、初年度は約20名が入社してきてくれましたが、
その頃から、少しずつコミュニケーションの取り方や接し方に悩みが出てきたんですね。
これまでと違って、距離感(関係性)を縮めていくプロセスが必要になってきました。
何かの業務にあたるにしても、これまでは「とりあえず現場に行って説明を聞いて」と伝えればよかったのですが、
それでは動けないことがわかりました。
事前に目的を伝えて、一緒に準備をして、という丁寧なプロセスを経ていく必要があるのだと...。
そのためには、私たちが今までと同じコミュニケーションの取り方をしていてはいけない、
変わらなければならない、という意識改革も必要です。
相手や時代に合わせていかなければならないと感じました。
2つ目は、役職者と若手との間で、本音の意思疎通ができていなかったことです。
組織の"あるある"かもしれませんが...。
役職者は若手に積極的に発言してもらいたいと思っているので、若手が発言するのを待って、自分たちは動かずにいる。
一方で若手は、役職者の手前、遠慮して発言するのを控えている。
発言してもらいたいなら、役職者から発言して活性化させていく場づくりをする必要があるのに、
そういうことも含めて、若手に積極的にやってもらいたいと期待してしまっていました。
若手にしてみれば、そのように期待されているとしても、簡単なことではないと思います。
どちらの課題も、「意識改革」と「関係性を築くこと」、この2つが必要です。
そのための取り組みは積極的に行うようにし、講座を導入して促進につなげています。
風通しの良い社風を作るコミュニケーションの秘訣

▲毎年ライブハウス等で開催している創立記念日の『GIG』 明るい社風と関係性の良さは◎
― 御社はスタッフの方が皆さん楽しそうで、
コミュニケーションがかなり活発に行われている印象があります。
このような環境にするために、どのようなことに取り組まれていらっしゃいますか?
教育以外の部分では、コロナ禍で控えたこともありますが、チームや社内でのイベントを積極的に行っていました。
夏のお疲れ様会、クリスマス会、忘年会。
新年の仕事初めは30~40名くらいで初詣に行って、一緒に朝食を食べてから出社したり、
創立記念日には「GIG」という会議を兼ねたイベントを行います。
チーム単位での交流も多くて、プライベートのことや自分の興味関心についてよく話しますし、
相手の興味関心もよく知っていると思います。
特にスポーツやコンサートなどのイベント運営を行っていますので、弊社では好きな野球チーム、
サッカーチーム、アーティストなどの話題がかなり出てくると思います。
誰かがあるスポーツチームのファンだと聞けば、「あの部署の誰々さんも同じだよ」という話がすぐに伝わって、
入社早々に共通項が作られることも多いです。こうした環境は特徴的なことかもしれません。
スタッフ同士で休日にコンサートに行ったり、スポーツ観戦にいくことも珍しくありません。
― コミュニケーションの教育面での取り組みや、工夫についても教えていただけますか。
コミュニケーション講座に関しては、これまでに100名強の社員全員が2級講座を受講しました。
アルバイトのスタッフも、希望者には受講を後押ししています。
準1級講座も役職者は全員受講していまして、年内には社員全員受講予定です。
スタッフ全員がコミュニケーションに関して、共通の理解を持っているだけでも、多くのことがスムーズに運びます。
さらに弊社ならではの取り組みは、講座を受講して終わりではなく、
講座受講後のフォローアップを継続して行っている点だと思います。
具体的には、講座で学んだことから、自分の行動課題を決めて取り組んでいく。
そして2〜3ヶ月ごとに振り返りを行うことをくり返しています。
フォローアップは、部署も年次もバラバラのチームを組んでいて、
そのチーム全員が行動課題を達成しよう、という目標を持って取り組んでいます。
コミュニケーションの学びは、人生の大きなアドバンテージになる
― 最後に、古木さんのこれからの目標をお聞かせください。
新卒で入社したメンバーが、じきに役職者になっていきます。
彼らが部下を迎えた時に、お互いがどう接すればいいのかであったり、
どうすれば人のやる気を引き出すことができるか?
ということを伝えて行きたいです。
新たな研修事業の構想では、企業だけでなく、
学校でのコミュニケーション教育にも携わっていきたいという思いがあります。
コミュニケーション講座で学ぶようなことは、人生の早いうちに学べたら、
どれほどのアドバンテージになるだろうか、
どれだけ人間関係が豊かになるだろうか、と思うのですよね。
私はみんながこれを知ったら、争いがなくなっていくはず!と思っていますし、
講座を開催していくことで、それに貢献していきたいと思っています。
そして学生さんには、「学ぶことは楽しい」「役に立つ」ということを
知っていただきたいです。

古木さんが受講されたのは、基礎にあたる「2級講座」から最上級の「トレーナー育成コース」まで。
ご自身でトレーナー資格を取得し、社内に資格講座を導入なさっています。
※心理学NLPについてご興味をお持ちの方は、こちらの「NLPとは」をご覧ください。
(関連団体のページが開きます)
コミュニケーション能力認定協会
当協会でこれまでに
14,000名以上の方が資格を取得されました。
ここでしか受講できない
一生の財産となる学びをご提供しています。