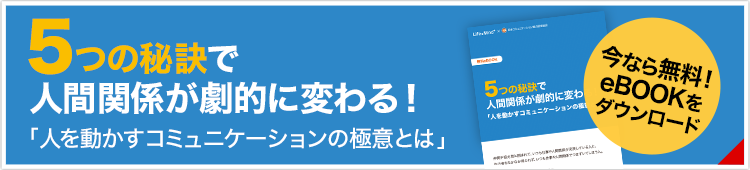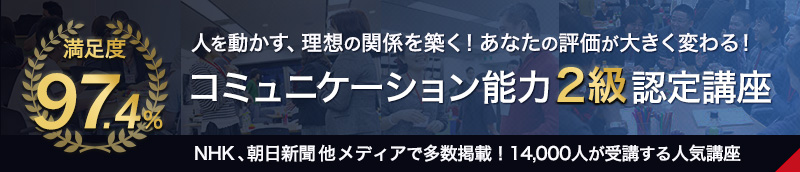心理的安全性とは?高め方も5つ紹介。鍵はコミュニケーションにあり

より生産性の高いチームや
組織を作る上で重要なことは、
心理的安全性があるかどうかです。
働いた期間やメンバーが誰かどうかは、
意外にも関係ないことなのです。
心理的安全性が高いことで、
自由な発言やよりよいアイデアを
生み出すことができるようになり、
より高い結果を残すことが
できるようになります。
そんな心理的安全性について、メリットや
低下したときに引き起こされる不安、
代表的な高め方など徹底解説いたします。
さらに6章では、心理的安全性の鍵となる
コミュニケーションについても
ご紹介しています。
ぜひ、最後までご覧ください。
1.心理的安全性とは
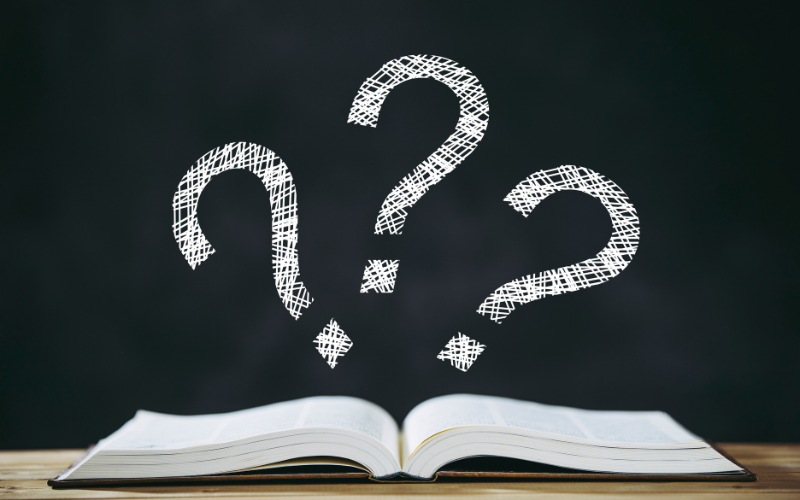
1-1.心理的安全性の定義
心理的安全性とは、チームや組織内で、メンバーが罰せられることや拒絶されるなどの不安がなく、
自分の意見やアイデアを表現することができる状態のことを指します。
心理的安全性(psychological safety)は、1999年にエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念であり、
チームや組織をより良くするために重要な概念であると考えられています。
社員と企業の双方にメリットがあるため、様々な企業で重要視されている概念です。
(参考資料)
エイミー・エドモンドソン: 他人同士の集まりをチームに変える方法 | TED Talk
1-2.心理的安全性とぬるま湯組織の違い
心理的安全性と聞くと、ただなんでも言えるようなアットホームな雰囲気があり、居心地の良い状態と思われることがあります。
いわゆる『ぬるま湯組織』と勘違いされてしまうのです。
しかし、この心理的安全性とぬるま湯組織との大きな違いがあります。
ぬるま湯組織では、居心地の良さや、和気あいあいとした雰囲気を守るために、意見が対立しないように自身の考えを押し殺し、相手の間違いを指摘することがない状態です。
さらに、メンバーには成長意欲はそれほどなく、現状維持を求めている場合がほとんどです。
一方で、心理的安全のある職場では、自身の意見を主張しながらも他者の意見も受け入れ、よりよいものにしようとメンバー1人1人が高い意欲を持っている状態です。
このように心理的安全性がある職場では、高い生産性、成長が伴います。
ぬるま湯組織とならないよう、メンバーの1人1人が意欲をもっていることが重要です。
2.心理的安全性が注目されている背景

ではなぜ、近年、心理的安全性はこれほどまで注目されるようになったのでしょうか。
様々な理由はありますが、大きな理由として、Google社がこの心理的安全性について言及したことがきっかけとされています。
Google社は、効果的なチームをつくるための重要な要因を調査しました。
その結果、効果的なチームを作るためには、
『誰がメンバーかではなく、チームがどのように協力しているかが重要である』
と発表しました。
さらに、チームへ影響を与える重要な要因を5つ発表しました。
重要な順に『心理的安全性』、『相互信頼』、『構造と明確さ』、『仕事の意味』、『インパクト』としました。
これまで、働いていた期間やチームメンバー個人のパフォーマンス、仕事量などが注目されていたために、この発表は社会に大きな影響を与えました。
このようなGoogle社の発表を受け、様々な企業で、最も重要とされる心理的安全性が注目されるようになったのです。
(引用資料)
Google re:Work - ガイド: 「効果的なチームとは何か」を知る
3.心理的安全性が高いことの8つのメリット

では、心理的安全性が高いことで、ビジネスシーンではどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、企業や従業員における、心理的安全性が高いことによる代表的な8つのメリットをご紹介します。
3-1.情報交換が活発になる
心理的安全性を高めることで、情報交換が活発になります。
定義の部分でもお伝えしましたが、心理的安全性が高い状態では、安心して自身の意見を表すことができます。
そのため、チーム内での情報交換が活発になり、よりスムーズに業務を進めることができるようになるだけでなく、より高い結果を生み出すことができるようになります。
さらに、情報交換だけでなく、見つかった問題や失敗などの経験も安心して共有できるようになるため、他のメンバーの経験を基に対策をすることもできるようになります。
3-2.事業の幅が広がる
心理的安全性が高い状態は、メンバーが意欲を持って、安心して発言できるため、
今までになかったような斬新なアイデアや、それまで不可能だと考えられていたことから、思わぬ良いアイデアが生み出されることがあります。
メンバー1人1人が違う価値観や興味をもっているからこそ、自分では考えつかないような新たな発見や気づきを得ることができるようになるのです。
こうした自由な議論の中から、新たなビジネスチャンスが生まれ、事業の幅が広がることを期待できます。
3-3.様々なことに挑戦ができる
心理的安全性が低い職場では、挑戦すること自体を非難されるのではないか、新たな挑戦は否定されるのではないか、
もしくは失敗したら咎められるのではないか、などと考えてしまい、なかなか挑戦することができなくなってしまいます。
一方で、心理的安全性が高い職場では、お互いを認め合うことが基礎にあります。
そのため、自分の考えを安心して表現することができるため、新たなことにも挑戦しやすく、様々なことに挑戦することができるようになります。
3-4.責任感が生まれる
自分が発した意見や経験がチームや組織に影響を与えていることを実感することができ、
チームや組織の目標達成のために自分にできることはないか、より効率的な方法はないかと考えるようになります。
そのため、業務に携わることへの責任感や役割意識を持って働くことができるようになります。
さらに、1人1人が責任感を持って働くことで、互いに高め合い、より高い成果を残すことができるようになります。
3-5.高いモチベーションが保てる
心理的安全性が高いと、チームや組織のメンバーが高いモチベーションを保つことができます。
心理的安全性が高い職場では、自分の意見を聞いてもらえるということを実感できるため、主体的に行動することができるようになります。
主体性を持って行動できることで、やりがいや達成感を感じ、モチベーションを高いまま保つことができるようになります。
3-6.作業効率が上がる
様々な意見を発言できるため、これまでの経験や工夫してきたことなども、チームや組織内で共有することができます。
そうすることで、作業効率を高めるための新たな工夫を見出すことが可能になります。
さらに、先にもお伝えしましたが、心理的安全性が高いと1人1人の責任感が生まれ、互いに高め合うことができるようになるため、
個人のパフォーマンスが向上し、作業効率が上がるようになるのです。
3-7.ストレスが低減する
自分の意見を押し殺すことなく、他者と共有することができたり、自分の意見が受け入れてもらえるという感覚があるため、
ストレスを感じることなく、自由に発言することができます。
さらに、他者との交流が活発になるため、悩みや不安も安心して話すことができるようになります。
他者に聞いてもらえているという感覚はストレスを低減させてくれます。
3-8.離職率の改善
心理的安全性が高いことで、離職率を改善することも期待できます。
先にもお伝えしたように、心理的安全性が高いことで、チームや組織内で主体性を持って働くことができ、やりがいを感じることができるようになります。
そのため、『この会社で働きたい』『このチームに貢献したい』という気持ちが生まれ、優秀な人材に長く働いてもらうことができるようになります。
4.心理的安全性が低下することで生まれる4つの不安

エドモンドソン教授によると、心理的安全性が低下する、つまり、否定されるのではないか、拒絶されるのではないかという状態では、
下記4つの不安が生まれるとされています。
- 1.無知だと思われる不安
- 2.無能だと思われる不安
- 3.邪魔をしてると思われる不安
- 4.ネガティブだと思われる不安
それぞれの不安についてご紹介します。
4-1.無知だと思われる不安
無知だと思われる不安とは、自分の発言や行動から、「何も知らないのだな」、「こんなことも分からないのか」と無知に思われてしまうのではないかという不安のことです。
この不安から、同じチームのメンバーに、業務における疑問や悩みを話すことができなくなり、解決できない状態のままとなってしまいます。
さらに、分からないまま業務に取り組むこととなり、ミスやトラブルに繋がってしまうこと、そもそも問題に気付けないという事態となってしまいます。
4-2.無能だと思われる不安
無能だと思われる不安とは、自分の言動から、「仕事ができない人だ」、「こんなこともできないのか」と能力がないと思われてしまうのではないかという不安のことです。
この不安があると、ミスをしてしまった際や、トラブルが起きてしまった際に正直に伝えることができなくなってしまいます。
その結果、ミスやトラブルがそのままとなり、さらに大きな問題へと発展してしまうことがあります。
4-3.邪魔をしてると思われる不安
邪魔をしていると思われる不安は、会議や話し合いの際に、自分の発言が「的はずれだな」、「論点と違う」など、迷惑に思われてしまうのではないかという不安です。
これにより、自発的に意見を述べることや自由な発想ができなくなってしまい、様々な意見が出なくなってしまいます。
様々な意見が出ないままでは、新たなアイデアやより優れた方法などを追求することができないのです。
そして、生産性は向上せず、新たなビジネスチャンスも掴むことができないままとなってしまいます。
4-4.ネガティブだと思われる不安
ネガティブだと思われる不安とは、リスクや間違いを指摘したことにより、
「細かい(神経質な)人だ」、「マイナスのことばかり言う」などのネガティブな印象を持たれてしまうのではないかという不安です。
これにより、リスクや間違いに気づいた時点で声を上げることが少なくなり、十分にリスクを解消できないまま、決定が行われてしまうのです。
さらに、より効率的な方法を思いついたときにも、このネガティブだと思われる不安があると
今までの方法を否定しているように思われてしまうと考え、効率化から遠のいてしまう原因にもなります。
(参考資料)
Building a psychologically safe workplace | Amy Edmondson | TEDxHGSE
5.心理的安全性を高める5つの方法
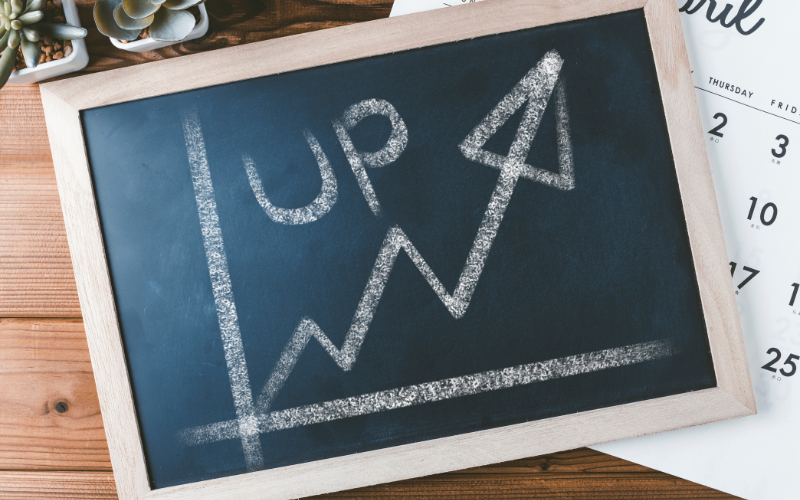
ここまで、心理的安全性についてメリットや、低いことで生じる不安についてお話してきました。
そんな、心理的安全性を高める方法はいくつかありますが、その中でも効果的なものをお伝えします。
5-1.積極的にコミュニケーションをとる
心理的安全性を高めるには、積極的なコミュニケーションはかかせません。
メンバーに自分の意見や行動を否定されることなく、受け入れてもらえるという安心を感じてもらうには、会話を通して、受け入れていることを伝えていく必要があるのです。
さらに、日頃から積極的にコミュニケーションを取ることで、気軽に話かけやすい雰囲気を作ることができます。
話しかけやすい雰囲気があることで、報告や連絡、相談がしやすくなります。
4章でご紹介した不安を軽減することができるのはコミュニケーションなのです。
しかし、コミュニケーションはただ一方的に取ればいいのではなく、人の心理的特性を活かすことで、より効果を発揮します。
詳しくは6章でお伝えします。
5-2.相談しやすい環境を整える
4章でお伝えしたように、不安がある状態では、新しい意見を出すことも、より高い成果をあげることも難しくなってしまいます。
そこで、チームのリーダーや上司となる役職者が、不安や悩みがあった際に、気軽に相談してもらえるような環境を作ることが必要です。
身近に仕事について相談できる、頼れる存在がいることは、心理的安全性を高めることに大きく繋がっていきます。
具体的には、例えば、毎朝10時~11時までの間は相談などができるよう、気軽に声をかけていい時間を設けることや、
『1on1』という1対1で対話を通して行う面談を実施することなどがあげられます。
しかし、突然悩みや不安について尋ねられると身構えてしまうこともあるため、
日頃からコミュニケーションを心がけ、相談しやすい雰囲気を作っていくことも重要です。
5-3.信頼関係を築ける交流の場を作る
心理的安全性には、メンバー同士の信頼関係は非常に重要です。
信頼関係が築けていないままでは、コミュニケーションを積極的に取っても、いくら相談の場を設けても、
疎外感や孤独を感じ、自分の意思を表現することが億劫になってしまいます。
信頼関係を築くための交流の場として、『Good&New(グッドアンドニュー)』というものがあります。
これは、24時間以内にあった良いことや新しい発見などをシェアするアイスブレイクの1種です。
メンバーの 『Good&New』を聞くことで、日頃からどのようなことに興味があるのか、どのような価値観をもっているのかを知ることができるようになります。
相手と自分の共通点を発見することできたり、共通の話題を見つけることができるようになり、親近感を感じるようになります。
そこから、コミュニケーションが発展し、信頼関係を築くことができるようになるのです。
この『Good&New』を会議やミーティングの開始前の10分間など、短時間でも取り入れることで信頼関係だけでなく、
事前に緊張感やマイナスな気持ちを軽くし、発言しやすくなるという効果があります。
5-4.発言の機会を平等に設ける
心理的安全性を高める方法として、チームでの話し合いや議論の場で、1人1人に発言する機会を設けることが効果的です。
心理的安全性が低い状態では、なかなか自ら発言することができず、より不安や疎外感を感じてしまいます。
さらに、偏った発言回数によって、『自分の意見なんてなくてもいい』と発言することができなくなってしまいます。
そこで、司会役やリーダーが平等に発言する機会を設け、発言を促すことによって、徐々に自発的に発言できるようになります。
そこから、発言しても否定されない、自分の意見も聞き入れてもらえるのだと安心することができます。
この安心感を積み重ねていくことで、1人1人の心理的安全性が高まり、チームとしての議論も活発になっていき、生産性の向上を期待できます。
5-5.評価制度を随時見直す
評価制度を見直すことも、心理的安全性を高めることに効果的とされています。
評価制度が成果ばかりを重視するものだとすると、「こんな発言をしてしまったら評価に影響してしまうのではないか」と考えてしまうことがあります。
また、チーム内での話し合いの際に、『話し合いでは全く発言しない人が評価されているのだから、自分も発言しなくていい』と考えて、
発言しなくなってしまうということが起こりうるのです。
こうした状況を改善するためにも、一度評価制度を見直し、時代や会社の価値観に沿ったものへとアップデートしていくことが必要です。
6.心理的安全性を高める鍵となるコミュニケーションとは

ここまで、心理的安全性を高める代表的な方法5つをお伝えしてきましたが、どの方法にもコミュニケーションは欠かせません。
つまり、心理的安全性を高めるために最も重要なことはコミュニケーションといえます。
しかし、5-1でもお伝えしましたが、コミュニケーションはむやみに取ればいいということではありません。
人の心理的特性を押さえたコミュニケーションを取ることが何よりも重要なのです。
人の心理的特性に基づいたコミュニケーションとは、相手の自己重要感を満たすようなコミュニケーションです。
人は誰しも、誰かに価値のある存在だと思われたい、自分自身を価値のある存在だと思いたいという自己重要感を生まれながらに持っています。
このような人間の深層心理を理解し、それに基づいたコミュニケーションをとることが必要なのです。
皆さんも初対面にも関わらず、「何となくこの人といると居心地がいいな」、「この人にはなんでも話せそう」と感じた経験が一度でもあるのではないでしょうか。
そう感じさせる人は、人の心理的特性を十分に理解し、適切なコミュニケーションを取っているのです。
さらに、こうしたコミュニケーションを取ることで、どのような場面でも信頼関係を築くことができるようになります。
人の深層心理に基づいたコミュニケーションをとるため、普段のコミュニケーションよりも好感や安心感を感じさせることができるようになり、信頼関係を築くことに繋がります。
当メディアサイトを運営する日本コミュニケーション能力認定協会では、
心理的安全性を高める鍵となる、心理的特性に着目したコミュニケーションについて、効果的に学ぶことができる資格講座を開催しています。
もしご興味をお持ちでしたら、まずは資格取得のメリットをご覧ください。
↓
今必要な「コミュニケーション能力」 ー資格取得のメリットー - コミュニケーション資格講座・検定
7.最後に
心理的安全性についてメリットや低下してしまう時起こる不安、高め方などをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
日々のちょっとしたコミュニケーションでも、心理的安全性は高まっていきます。
ぜひ、人の心理的特性を押さえたコミュニケーションを実践してみてください。
コミュニケーション能力を高めたいとお考えの方は、日本コミュニケーション能力認定協会が制作・監修した、下記の無料eBOOKがお役に立てると思います。
ご興味をお持ちの方は、こちらをチェックしてみてください。
↓
【無料eBOOK】5つの秘訣で人間関係が劇的に変わる!「人を動かすコミュニケーションの極意とは」
(参考資料)
Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams
【eBOOK】今なら無料プレゼント
人間関係が劇的に変わる
コミュニケーション
『5つの秘訣』とは?
人間関係や仕事でうまくいく人と、そうでない人の
コミュニケーションには、どのような違いがあるのでしょうか?
この無料eBOOKは、両者の違いを探求して見出した、
コミュニケーションがうまくいっている人たちの
「共通点」や「秘訣」の一部をまとめたものです。
- 部下やチームをもっとうまくまとめたい
- 営業や接客・販売の成績をもっと上げたい
- 人を巻き込む力・人を動かす影響力を身につけたい
- 言いたいことが伝わらずに悔しい思いをしている
- 家族や恋人との関係をもっと良くしたい
1つでも当てはまることがある場合は、
このeBOOKがきっとお役に立てることでしょう。
今すぐ下記からダウンロードして、ご活用ください。