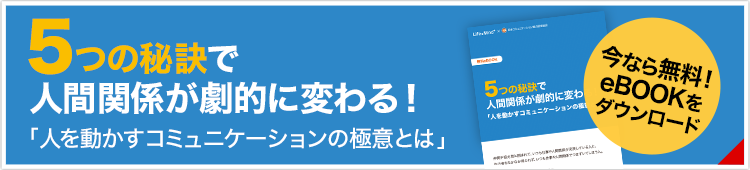プレゼン構成 5つの基本とは/絶対に知っておきたいプレゼンの構成要素

プレゼンテーションを作成するとき
伝える内容とともに考えることが
「構成」です。
プレゼンの構成は、
一度いくつかの型を知っておくだけで、
どんなプレゼンにも応用可能です。
本記事では、プレゼンの構成が
いかに重要かを確認した上で、
代表的な構成を5つご紹介いたします。
1.プレゼンにおける構成の重要性

まず、プレゼンにおいて構成がどれほど大切なのかを、一度確認してみましょう。
あなたがプレゼンを作成するにあたって、大切にしていることは何でしょうか。
多くの方が、「伝える内容」と答えるかもしれませんが、実は、内容の前に大切なことがあるのです。
有名な「メラビアンの法則」によると、話し手が発した情報のうち言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%の割合で聞き手に影響を与えるといいます。
つまり、全ての情報が一貫していることを前提として、話している内容よりも話し方や見た目が整っていることの方が相手へ大きく影響しています。
そして、構成はプレゼンの土台になるため、どのような構成を選択するかによって、話し方やスライドの見せ方も変わってきます。
したがって、せっかく内容が良くても、構成が悪くてなかなか伝わらない…という場合も考えられます。
一方で、構成を変えるだけで一気に相手に伝わりやすい、刺さるプレゼンへ変えることもできるのです。
2.構成を考えるポイント

具体的な構成を考える前に、まずは構成を検討するにあたって押さえておきたい2つのポイントをご説明いたします。
2-1.相手の立場に立って考える
構成を決定する前に、まずはプレゼンの聞き手について考えます。
聞き手の立場に立って、聞き手が何を求めているのか、どのような視点でプレゼンを聞くのかを把握することで、プレゼン内容が届いて欲しい人にピンポイントで刺さるプレゼンを実現することにつながります。
また、何をどのように伝える必要があるのかを予め知っておくことで、ベストな構成を選択することが可能になります。
聞き手のことを理解するために、事前に考えるとよいポイントは、下記のものがあります。
【聞き手について考えるポイント例】
性別、年齢、職種、所得、学歴、趣味、世帯規模、ライフスタイル、思考、悩み、ストレス、願望、価値観…etc.
2-2.概要→詳細の順番で話す
もう1つ確実に抑えておきたいポイントは、先に概要を話し、その後に具体的内容や詳細を話すことです。
人が話を聞くときや行動を起こすときには、大きく2種類のタイプがいると言われています。
話題やこれから取り組むことの「全体を把握してから実行したいタイプ(全体型)」と、「細かいプロセスまで確認後に取り組みたいタイプ(詳細型)」です。
そして、プレゼンの聞き手を複数名と想定する場合には、全体型・詳細型どちらにも伝わるような構成を考えることが重要です。
基本的に全体型の方々は全体像がわからないと話を聞く気力がなくなってしまい、詳細型の方々は詳細がわかるまで話を聞いてくれる傾向にあります。
そのため先に話の全体像を伝え、その後詳細な話へ進めていく方法をとると、どちらのタイプの方へもプレゼン内容が伝わりやすくなります。
実際に、この後ご紹介する構成を確認しても、概要や主張を先に述べてから、詳細の話を進める順番で組み立てられています。
3.代表的な構成5選

構成の重要性、考えるポイントを抑えたうえで3章では、代表的なプレゼンの構成を5つご紹介いたします。
自分が行う予定のプレゼンにはどの構成が適しているのか想像しながら読んでみると、あなたにぴったりな構成を見つけることができるでしょう。
3-1.三段構成
「序論→本論→結論」の順番に3段を組み立てる、最も基本的な方法です。
プレゼンテーションだけでなく、論文など自分の主張を伝える場合に用いられます。
各段で話す内容は、下記のとおりです。
①序論
- テーマや問題の提示
- 自分の主張
②本論
- 例やデータ、主張の理由など、
- 伝えたい具体的な内容
③結論
- 自分の主張
- プレゼン全体のまとめ
例:
①序論
今回は三段構成についてお話いたします。
私は三段構成は、最もシンプルで有効なプレゼンの構成だと考えます。
②本論
その理由は…
三段構成が効果的な場面として…
具体的には…
③結論
まとめると、三段構成はプレゼンの構成として最もシンプルで有効な方法だと考えます。
そして、具体的な活用場面などについてお伝えしました。ご清聴ありがとうございました。
3-2.SDS法
SDS法は、「Summary(概要)→Detail(詳細)→Summary(全体的なまとめ)」の順番でまとめる方法です。
シンプルな構成のため、どんなプレゼンテーションでも活用できます。
また、Detail(詳細)の中にSDSの小さなかたまりや他の構成を組み込むという応用も効きます。
SDS法の例は下記になります。
①Summary(概要)
今回はSDS法についてお話します。
SDS法はプレゼンの構成の1つです。3つの内容で構成されます。
②Detail(詳細)
1つ目は、概要です。ここでは…
2つ目は、詳細です。具体的には…
3つ目は、全体的なまとめです。内容は…
実際に活用する例としては…
③Summary(全体的なまとめ)
以上、SDS法についてお話しました。
SDS法は、概要・詳細・全体的なまとめの3つで構成される方法でした。
ぜひご活用ください。ご清聴ありがとうございました。
3-3.PREP法
PREP法は説得力が高まる方法で、下記の構成でプレゼンを行います。
①Point(結論・要点)
結論や要点を述べる
②Reason(理由)
その結論の理由を伝える
③Example(事例・具体例)
事例や具体的理由を伝える
④Point(結論・要点)
再度、結論や要点を伝える
実際のプレゼンの場面では、下記のように行います。
①Point(結論・要点)
プレゼンテーションの構成として、PREP法が有効です。
②Reason(理由)
なぜなら、説得力のあるプレゼンを作成することができるからです。
③Example(事例・具体例)
PREP法の具体的な構成は…
例えば○○についてプレゼンするときは…
④Point(結論・要点)
以上、PREP法がプレゼンテーションに有効な構成であることをご紹介しました。
PREP法は、口頭でのプレゼンテーションに加えて、文章での説得にも活用可能です。
3-4.DESC法
DESC法は相手を尊重しつつ、自分の意見を伝えたい場合に有効な構成です。1対1のコミュニケーションでも効果的に利用できます。
具体的には、下記のような順番で構成されます。
①Describe(描写)
状況を客観的に描写する。事実を伝える。
②Explain(表現)
表現する。自分の気持ちを説明する
③Specify(提案)
提案・お願いをする
③Choose(結果)
選択する。結果を示唆する。
例:
①Describe(描写)
我が社では現状、〇〇が課題となっています。
原因は…。
具体的には△△で…。
②Explain(表現)
私としては、〇〇は深刻な課題になっていると考えるため、
□□のように考えています。
③Specify(提案)
以上を踏まえまして、〇〇に対し、××という改善策を提案いたします。
その内容は…。
④Choose(結果)
今回の改善策が採用される場合には、▲▲のように進めます。
もし不採用の場合には、代わりに他の改善策を提案し、後日改めてご説明いたします。
3-5.4MATシステム
4MATシステムは、もともと研修等のコースデザイン理論だったため、
講座開催やセミナー、研修などへの登壇としてプレゼンを行う方へおすすめの構成です。
観衆がプレゼンに興味をもつ内容と聞き手全体に対する割合に基づいて下記のように順番が組み立てられています。
| 【1】Why(なぜ) |
|---|
| なぜ知る必要があるのか どんないい影響があるのか |
| 【2】What(なに) |
| 具体的な情報 |
| 【3】How(どのように) |
| 具体的な方法や手順 |
| 【4】If(もし) |
| 他の場合で活用できるか |
※参照元:12期全米NLP協会公認NLPトレーナーズ・トレーニングテキスト
例:
Why
今日は〇〇についてご紹介します。
ご紹介する理由は…。
この内容を知ると△△な場面で役立ちます。
What
〇〇とは…。
その内容は…。
例としては…。
How
では、具体的な方法をお伝えします。
まず…。次に…。そして…。
If
この方法は他にも□□の場面などで活用できます。
もし××という問題がある場合には…。
応用例としては…。
お伝えすることは以上です。ご清聴ありがとうございました。
以上、代表的な構成を5つご紹介いたしました。あなたに合った構成を選んでぜひご活用ください。
4.よりよいプレゼンにするために

本記事では、プレゼンにおける構成の重要性や構成を考えるポイントを確認した上で、プレゼンでよく利用される、代表的な構成5つをご紹介いたしました。
皆さんの目的や届けたい内容にあった構成が見つかっていると幸いです。
そして、構成を考えたら、話の内容や伝え方を検討するフェーズに入り、自分の見せ方や話し方を研究することになります。
もし、大勢の前で話すこと苦手意識があったりコミュニケーションに課題を感じていたりする場合には、私たちの『コミュニケーション能力認定講座』で学べる内容がお役に立つかもしれません。
日本コミュニケーション能力認定協会では、1対1から1対多でのコミュニケーション、また基本的な信頼関係の築き方や上級のコミュニケーションスキルまで、あらゆる場面を想定したコミュニケーションについて実践を通して学ぶ講座を開講しています。
講座へは、経営者の方やビジネスパーソン、著者、弁護士、医者、学校の教員、営業をされている方、学生の方など、様々な方が学びにいらしています。
コミュニケーション能力の向上にご興味をお持ちの方は、多くの方がダウンロードされている【無料eBOOK】をご覧いただくか、
最短1日から参加できる【コミュニケーション能力認定講座】にご参加ください。
【eBOOK】今なら無料プレゼント
人間関係が劇的に変わる
コミュニケーション
『5つの秘訣』とは?
人間関係や仕事でうまくいく人と、そうでない人の
コミュニケーションには、どのような違いがあるのでしょうか?
この無料eBOOKは、両者の違いを探求して見出した、
コミュニケーションがうまくいっている人たちの
「共通点」や「秘訣」の一部をまとめたものです。
- 部下やチームをもっとうまくまとめたい
- 営業や接客・販売の成績をもっと上げたい
- 人を巻き込む力・人を動かす影響力を身につけたい
- 言いたいことが伝わらずに悔しい思いをしている
- 家族や恋人との関係をもっと良くしたい
1つでも当てはまることがある場合は、
このeBOOKがきっとお役に立てることでしょう。
今すぐ下記からダウンロードして、ご活用ください。