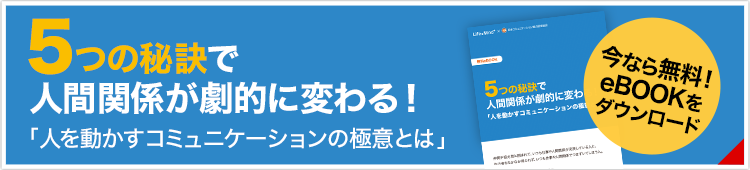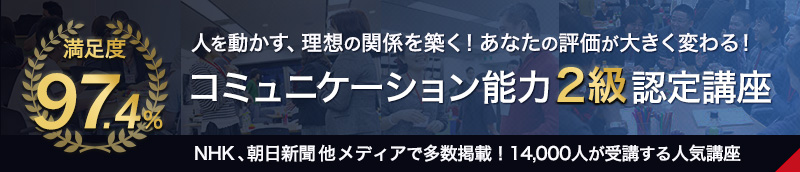【効果絶大】傾聴力を高めるトレーニング5ステップをご紹介
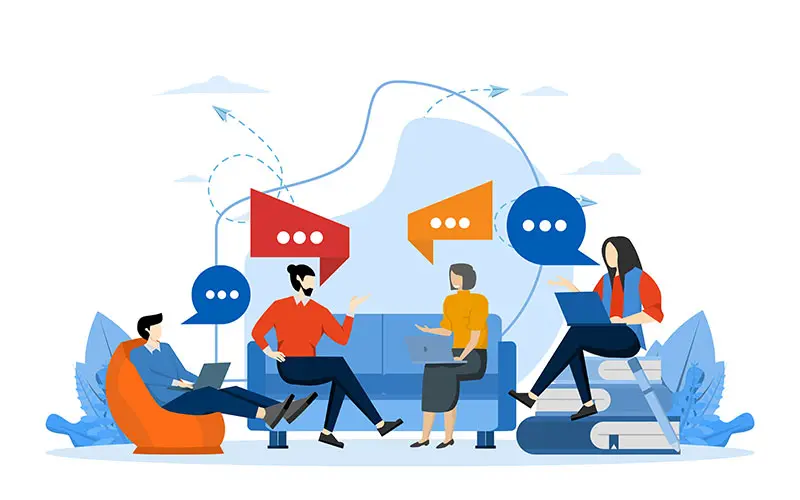
人間関係を円滑にするために、
傾聴力のトレーニングは欠かせません。
初対面の人との信頼関係を築くため、
そして現在の人間関係をより良くするために、
あなたは、普段の日常生活で
正しく『傾聴』ができていますか?
人は自分の話を聴いてもらえると
満足感を得られる生き物です。
そのため、良好な人間関係を築くために
『傾聴スキル』は必須です。
傾聴は、ただ相手の話を
聴くだけのスキルではありません。
傾聴スキルを磨くことで、相手の心を
グッと掴んでうまく働きかける効果を
発揮することができます。
もし今、あなたが下記のような悩みを
お持ちであっても問題ありません。
- 相手との会話が広がらない
- 信頼関係を築きたいのに、
踏み込んだコミュニケーションが取れない - 相手の言葉へ何と切り返していいか
わからない
この記事では、傾聴スキルの初級から
上級まで、『傾聴力を高めることに特化した
トレーニング法』をご紹介していきます。
傾聴力に自信のない方も、
自信がある方も、ぜひ実践してみてください。
1.傾聴力を高める効果とメリット
傾聴力を高めることができると、具体的にどのような効果が得られるのでしょうか?
【傾聴力を高める効果とメリット】
- 社内で立場が異なる相手から、本心を話してもらえるようになる
- 営業や接客でクライアントが「あなたのファン」になり「あなたから買いたい」と言ってもらえるようになる
- 夫婦間やパートナーと、しっかり向き合って本音で話し合える関係になる
「傾聴力を高めるだけでこんなにも効果があるの?」という疑問が浮かぶかもしれませんが、傾聴力を侮ってはいけません。
傾聴力は信頼関係の核とも言えるスキルです。
傾聴力を磨けば磨くほど、その効果を実感できるでしょう。
もう少し具体的にご説明していきます。
1-1.社内の人間関係における傾聴の効果
会社では、上司・部下という立場があります。
立場が違うことで、考えもそれぞれ異なるので、組織を円滑にしていくためには「相手の立場を理解する姿勢」が必要不可欠となります。
特に、上司・部下の関係性では、上司は部下の話を傾聴して丁寧に接することで、部下も「この人はしっかり話を聴いてくれる人だ。」と信頼関係が生まれるようになり、
「この人になら話ができる」と、新しいアイディアや提案も活発に行き交うような関係を作ることができるようになります。
1-2.営業や接客における傾聴の効果
傾聴力を高めて注意深くクライアントの言葉に耳を傾けることで、クライアント自身も把握できていなかった真のニーズを理解し、クライアントに対して、的確なアプローチをすることができるようになります。
また、クライアントの話を丁寧に聴くことで、「この人からまた買いたい。この人が言うのなら買ってもいいな。」とクライアントとの信頼関係を築くことができるようになります。
1-3.プライベートにおける傾聴の効果
家族や友達など、プライベートにおける傾聴も大切です。
身近な人だからこそ、「きっとわかってくれているだろう。」と雑な傾聴になってしまっていないですか?
夫婦間においての傾聴で例をあげると、
-
何でこんな大事な話を相談しなかったんだ?」
-
だってあなたいつも私の話を聞かないじゃない。」
こういった会話をどこかで聞いたことはありませんか?
普段から関心を持って傾聴していれば、些細なことでも相談する事ができ、いざ大事な局面になっても夫婦で乗り越える事ができるのです。
2.傾聴の種類

傾聴は3つのステージで身につけることができます。
それぞれの段階で、相手の話を十分に聴けるようになったと思ったら、次のステージに行きましょう。
- 1:受動的傾聴 相手の話を丁寧に聴き続ける
- 2:反射的傾聴 相手の状態に合わせて反応して聴く
- 3:積極的傾聴 相手に働きかけるように聴く
3.速攻で傾聴力を高める5つのトレーニング方法

ここからは、速攻で傾聴力を高めることができる、傾聴トレーニング方法を段階別でお伝えします。
職場の人間関係で悩んでいる方、営業職でクライアントと信頼関係を築きたい方、家族間やプライベートでの関係を充実させたい方、ぜひこのトレーニングを実践してみてください。
3-1.【ステップ1】話しかけやすい雰囲気作り
私たちは普段、無意識のなかで、言葉を使った言語コミュニケーションと、言葉を使わないコミュニケーション『非言語コミュニケーション』の2つを使い分けて生活しています。
話しかけやすい雰囲気・話しかけにくい雰囲気。
これは、あなたが発している『非言語コミュニケーション』にあたります。
話しかけにくい人の姿勢
- 眉間に皺が寄っていて怖い。
- 話しをしても全く無反応に見える。
- 話しかけても目を合わせてくれない。
これでは、話しかけたくても話しかけづらい。
せっかく真剣に話していても、聴いてもらえていない。
相手からは、このように受け取られてしまっている可能性があります。
もしあなたが相談した相手から、このような姿勢を取られてしまったら、「この人は、真剣に受け止める気持ちがなさそう‥。次から別の人に相談しよう。」と思うことでしょう。
この様な人には、話しかけてもらいやすい雰囲気を意識的に作る事が大切です。
話しかけやすい人の姿勢
- 柔和な表情
- 相手の方へ体を向けて、目を見て話を聴く
- 相づち
できる限り『柔和な表情』で、話しかけられた時には『相手の方へ体を向けて、目を見て話を聴きましょう』
そして、時折『相づち』を打つことで、相手から『真剣に話を聴いてくれいている』『自分に共感してくれている』と思ってもらう事ができるようになります。
普段からこの姿勢を意識する事が大切です。
3-2.【ステップ2】ペーシング
傾聴スキルの1つとして「ペーシング」のやり方をお伝えします。
ペーシングとは、話す速さ・声の高さ・表情・感情を相手に合わせることです。
相手がゆっくり話しをしているのに、あなたが早口で切り替えしてしまうと、相手は戸惑ってしまいます。
逆に、相手が早口で話しているのに、あなたがゆっくり切り替えしてしまうと、相手はイライラしてしまう可能性があります。
また、相手が悲しそうに辛い経験を話しているのに、あなたが元気よく相槌を打ってしまうと、「この人は私の気持ちをわかってくれない」と思われてしまいます。
人は自分と共通する人に対して安心感を持つ生き物です。
相手のペースに合わせて反応するだけで、相手は「共感してくれている・真剣に話を聴いてくれている」と思ってもらうことができます。
このスキルは初対面の人に使うことができますし、相手からの第一印象にも良い影響を与えます。
そのためには、相手の事をよく観察することが大切です。
3-3.【ステップ3】オウム返しを使いこなす

傾聴力を高めることにおいて、実は『オウム返し』は最重要とも呼べるスキルです。
オウム返しは、相手の話す言葉を用いて返すことで、相手から『私の話に関心をもってくれている・しっかり聴いてくれている・共感してくれている』という安心感を持ってもらえるようになります。
オウム返しには、3つの種類があります。
- 事実にオウム返しする
- 感情にオウム返しする
- 要約してオウム返しする
1つずつ、例を使って説明していきますので、これを読まれているあなたも、「自分だったら何て答えるだろう?」と考えながらやってみましょう。
3-3-1.事実にオウム返しする
まずは、事実だけにオウム返しをしてみましょう。
相手の言葉をそのまま切り取って返すので、あなたの感想や気持ちは含めずに伝えます。
例
相手 :「昨日、映画館で新作の◯◯を観てきたんだ。すごく面白かったよ!」
あなた:「映画で新作の◯◯観てきたの?面白かったんだね~」
相手 :「そうなの!あまり期待してなかったんだけど、意外と面白くて~...」と続きます。
【事実のオウム返しの注意点】
- あなたの感想や気持ちは含めない
- 相手が使っていない言葉に変換しない
- 多用すると違和感を感じるので使いすぎない
事実のオウム返しは簡単に実施することができます。
なぜかと言うと、相手の言葉を用いているので、認識がズレることがないからです。
相手からも「話がスムーズに進む相手だ」と思ってもらえるようになります。
3-3-2.感情にオウム返しする
次に、相手の感情にオウム返しをしましょう。
これは、相手の感情を中心にオウム返しをする方法です。
例
- ①嬉しい
- ②悲しい
- ③腹が立つ
①嬉しい感情
相手 :「今日、部長から私の仕事褒めてもらえて、すごく嬉しくなっちゃった。」
あなた:「部長から褒められたんだ!それはすごく嬉しいよね。」
相手 :「そうなの!◯◯部長からはね~...」
と続きます。
②悲しい感情
相手 :「頑張って作っていた資料データが消えちゃってて、すごく悲しい。」
あなた:「頑張って作ったのに、それは悲しいよね。」
③腹が立つ感情
相手 :「昨日、◯◯さんから嫌味言われてすごく腹が立ってるんだよね。」
あなた:「嫌味言われちゃったんだ。それは腹が立つよね。」
事実のオウム返しと同じ様に、感情のオウム返しも相手の言葉をそのまま切り取って使うので、相手と話がズレることはありません。
相手から事実と感情をセットで伝えられたら、感情の方を優先的にオウム返しするようにしましょう。
人は感情に反応してもらったほうが嬉しく感じるためです。
【感情のオウム返しの注意点】
- あなたの感想や気持ちは含めない
- 相手が使っていない言葉に変換しない
- 多用すると違和感を感じるので使いすぎない
- 事実より感情のオウム返しを優先する
3-3-3.要約してオウム返しする
オウム返しの上級編になります。
先程までは、相手の言葉をそのまま切り取ってオウム返しをするようにお伝えしてきましたが、ここでは相手の言葉を適度に言い換え(要約)してオウム返しをします。
適度な言い換えとは、相手が使った言葉と同じ意味の言葉に変換することです。
適度に言い換える事でこのようなメリットがあります。
- 不自然にならない
- 次の会話が広がりやすい
- こちらの感情が伝わる
例(1)
相手 :「昨日、子どもたちと一緒にピクニック行ってきたんだけど、子どもがすごく喜んでくれてよかったよ。」
あなた:「お子さんすごく喜んでくれてくれたんですね。パパとしても嬉しいですよね。」
相手 :「そうなんだよ〜。最近あまり外出できてなかったから~…」
例(2)
相手: 「先週フェスに行く予定だったのに、大雨のせいで中止になっちゃって悲しかった。」
あなた:「先週の雨すごかったからね。でもせっかく予定空けてたのに中止は残念だよね。」
相手: 「そうなの。この日のために準備してたのに~…」
いかがでしょうか。
例(1)では、「よかった」を「パパとしても嬉しい」に変換し例(2)では、「悲しかった」を「残念」と変換しました。
要約してオウム返しをするほうが、あなたの気持ちをのせやすいので、相手との会話は広がりやすくなりますが、
あなたの変換する言葉が、相手の放った感情と一致していないと、齟齬が起こってしまうので注意が必要です。
そのため、この要約のオウム返しを使いこなすために、まずは沢山練習して臨みましょう。
【要約のオウム返しの注意点】
- 相手が使う言葉と同じニュアンスで言い換える
- 変換しすぎると話がズレるので、変換しすぎない
いかがでしたか?ここまでオウム返しのトレーニング方法をお伝えしてきましたが、オウム返しは、使えば使うほど効果のほどは絶大です。
ただし、スキルを磨くためには、相手の話をしっかり傾聴することが大前提になります。
普段から、傾聴が身についている方なら簡単にできるスキルですが、
もし、この例題を実行してみて『難しい』と感じる方は、もしかすると、日常生活において『傾聴』ができていない可能性があります。
そのような場合、まずはしっかり傾聴することに意識を向けてみてください。
3-3-4.応用スキル「YESセット法」
要約のオウム返しが身についたら、更に上級のスキルに挑戦してみませんか?
今からご紹介する「YESセット法」は営業職の界隈では非常に有名なスキルで、『悪用厳禁』とも言われています。
やり方としては、相手から複数回のYESを取った後に本題に持ち込むと、商談が成約しやすくなるという話し方で、これは営業だけではなく、恋愛テクニックとしても使われています。
理解を深めていくために、具体例を紹介します。
下記は、アパレルショップの店員さんとお客様の会話を通して、お客様へ要約のオウム返しと、YESセット法を使った接客例です。
店員 :「なにかお探しですか?」
お客様:「最近寒くなってきたから、本格的なコートが欲しいなと思って見に来たんです。」
店員 :「昨日もすごく寒かったでよすね。こんなに寒いなら本格的に暖かいコート欲しくなりますよね。」
お客様:「そうなんです。いつも、ずっと買おう買おうと思いながら、結局買わずに春先になっちゃうんですよ。」
店員 :「買おう買おうと思っても、一番寒い時期を乗り越えちゃうと優先度下がっちゃいますもんね。」
お客様:「はい。だから今日は見に来たんです。試着してみないとわからないから。」
店員 :「暖かさとかは着てみないとわからないですからね。」
お客様:「そうなんです。」
店員 :「よかったら試着されてみますか?」
お客様:「おねがいします。」
さて、店員さんは、お客様から何回YESを取ったかわかりますか?
YESセット法の効果として、3回はYESを取ると、本題や交渉、クロージングに持ち込んだ際に相手からYESがさらに取りやすくなると言われています。
なぜ相手からYESが取りやすくなるのかと言うと、人は無意識の中で自分の行動や発言、態度などを一貫させたいという心理が働きます。
「YES」を繰り返し発することで、次の問いかけにも「YES」と言いたくなってしまうという事です。
これを「一貫性の法則」といいます。
例題では、店員さんはお客様に対して要約してオウム返しをしています。
つまり、多少の表現は違っても、相手が言いたいことをそのまま返していることになるため、お客様は、「YES」と言わざるを得ないのです。
そうです。このテクニックを使用すると、意図的に相手からイエスを引き出せるようになってしまうため、使い方次第では、『悪用厳禁』と言われているのです。
ですから、使い方にはくれぐれもご注意ください。
このスキルは傾聴力や観察力を高めなければ身に付けられない上級テクニックです。もしこのスキルを身につけたいと思われたら、ぜひ練習してみましょう。
3-4.【ステップ4】自己開示が信頼感を生み出す
傾聴のスキルは、相手の話を聴くだけではありません。
会話は常に相手とのキャッチボールです。相手の話を聴くだけでは、相手が心の内を話すまでの信頼関係を築くことは難しいでしょう。
相手が心の内を話せるようになるまでの『信頼感』を得てもらうためには、あなた自身の自己開示をすることも重要です。
社内での例として、あなたが部下と話している時を例にあげてみます。
部下:「昨日仕事でこんなミスをしてしまってすごく自信をなくしているんです。」と言われた場合
自己開示を入れない会話の場合
あなた:「ミスしちゃったんだ。それは自信なくしちゃうよね。こうする様にしたら、同じミスなくなるよ。」
自己開示を入れた会話の場合
あなた:「私も入社したばかりの頃、同じミスをしちゃってお客様から酷く叱られてしまったことがあるから落ち込む気持ちわかるよ。私もすごく落ち込んだし、自信もなくなったけど、こうする様にしたらミスが減ったよ。」
さて、どちらの返答のほうが『共感と信頼感』が生まれるかわかりますか?
先にもお伝えしたように、人は自分と共通している人に対し、好感を持ちやすい生き物です。
部下からすると、『自分と同じミスをして、自分と同じ気持ちになったことがある。』という安心感と、同じ状況に陥ったことがある人の助言は、受け取りやすく信頼につながります。
3-5.【ステップ5】答えやすい質問で会話を広げる

「深く関係が築けていない相手との会話が続かない」
こう悩んでいる人も多いと思います。
ここでは、会話を広げるための質問方法をお伝えします。
この質問スキルには段階があります。
基本・・事実を聴きだす「5W質問」
応用・・基本プラス感情を加えた質問
まずは、基本の5Wの質問です。
5Wとは、以下の事を指します。
基本の5W
- 時間(When)
- 人 (Who)
- 場所(Where)
- 特徴(What)
- きっかけ(Why)
例として、あなたが営業マンだとします。
クライアントと初めて対面するときをイメージしてください。
あなた:「初めまして。今日はどちら(場所Where)からいらっしゃったのですか?」
相手 :「今日は静岡から来ました。」
あなた:「静岡からですか。私も昔静岡の◯◯に遊びに行っていたことがあります。ちなみに静岡のどのあたりですか?」
相手 :「そうなんですね。私は静岡の◯◯市の方なんです。」
この様に、5Wを加えることで、会話とのキャッチボールがやりやすくなります。
次は、応用編として感情を加えた質問をしてみます。
あなた:「初めまして。今日はどちら(場所Where)からいらっしゃったのですか?」
相手 :「今日は静岡から来ました。」
あなた:「静岡からいらしたんですね。静岡は◯◯というご飯屋さんが有名と聞いて一度食べに行ったことがあるんですけど、すごく美味しかったので(感情)また行きたいと思っているんです。◯◯ご存知ですか?」
相手: 「はい。私も家族でよく行くんですよ。はすごく美味しいですよね。」
いかがですか?
ここでは「美味しい」という感情を使いましたが、感情をプラスした事で、次の会話も弾んでいく様子が浮かぶと思います。
他にも、楽しい・嬉しい・面白い・素敵・魅力的・最高。このような感情を入れることもできます。
感情をプラスして入れることで、このようなメリットがあります。
- 無難なやり取りにならない
- 相手の感情も引き出せる
- 会話が弾みやすい
このように、相手との会話を弾ませるためには、「相手の事を知りたい・関心がある」という気持ちを持って接しないと、感情を入れて質問をすることは難しいです。
相手から関心を持ってもらいたいなら、まずは自分から。この気持ちで接していきましょう。
このスキルを使いこなせるようになれば、相手からも「この人に関心がある」と思ってもらえるようになるので、自然と会話が広がり、深まっていきます。
4.傾聴力の低い人にありがちな5つのNG行為と対策

傾聴力を上げるトレーニングをお伝えしてきましたが、いかがでしたか?
次は、傾聴の際にやってしまいがちなNG行為を5つお伝えしていきます。
あなたがいくら傾聴のトレーニングを重ねても、以下の行為をしてしまうと、相手との信頼関係を壊してしまう可能性がありますので、自分に当てはまるところは無いか、チェックしてみましょう。
4-1.相手の顔を見ず会話をしてしまう
忙しいと、ついつい相手の顔を見ずに話をしてしまうことはあると思います。
今日会話した人の表情はどんな表情だったでしょうか。
笑っている顔でしたか?
困った顔でしたか?
もし、思い出せなかったとすると、相手の顔をしっかりと見て話せていない可能性があります。
相手の表情からは、話す内容だけではなく、本心や感情などといった多くの情報を受け取ることができます。
こうした観察力は傾聴のスキルを高めるうえでとても大切です。
心当たりがある場合には、まずは自身の話を聴く姿勢がどうなっているか、この機会に見直していきましょう。
4-2.相手の言葉を遮って自分の考えを言ってしまう
これは、上司部下の関係でよく見られるケースです。
なぜなら、上司は経験が豊富なため、たいていの場合、部下の質問や相談を聞いた瞬間から答えが頭に浮かんでくるからです。
そのため、部下が話し終えるよりも先に、自分の考えや答えを言ってしまう事が起きやすいのです。
効率的に見えるかもれませんが、部下としては「自分の話を最後まで聞いてくれなかった。」このような良くない印象が残ってしまう可能性があります。
もし、この傾向がある場合には、まずはじっくり傾聴して、オウム返しを意識的に実践していきましょう。
4-3.抑揚のない相づち
相手がせっかく一生懸命に話してくれているのに、「ふーん。」や「へー。」だけで会話を終わらせてしまっていませんか?
このような反応をしてしまうと、相手からは「真剣に聞いてくれていない」と思われてしまい、信頼関係が築きづらくなってしまいます。
もしあなたに思い当たる節がある場合には、ペーシングスキルを練習して、相手の状況や感情に合わせたコミュニケーションを取るように心がけましょう。
4-4.自分の話にすり替えてしまう
相手が話している途中にもかかわらず、自分の話にすり替えてしまい、結局自分だけが喋って満足してしまうような状態です。
あなたの周りにも、思い浮かぶ人がいるかもしれませんね。
近頃は「会話泥棒」とも呼ばれていますが、あなたは100%大丈夫だと言えるでしょうか?
周囲の人は気がついていても、当人は無自覚なケースが多いというのが、恐ろしいポイントです。
もし、あなたにも思い当たる節があるようでしたら、まずは相手の話を最後まで聴くことに集中しましょう。
そして、何度もオウム返しを実践しましょう。
4-5.沈黙が怖くて話し続けてしまう
営業職を経験されている方ならお分かりかもしれませんが、商談の際に、一通り商品の説明が終わると、クライアントが沈黙してしまう事があります。
これは、あなたのプレゼン力が低いからでは無く、クライアントは、あなたのプレゼンを聞いて『考えている』のです。
なので、焦って畳み掛けてはいけません。
クライアントにペーシングにして、相手へ思案する時間を設けてあげましょう。
いかがでしょうか。
あなたに当てはまっているものはありましたか?
傾聴力は、トレーニング次第で身につけることができます。
今回、当てはまっているものがあっても問題ありません。根気よく改善していきましょう。
5.まとめ
本記事では『傾聴力を高めるトレーニング方法』をお伝えしてきましたが、あなたの日常生活で実践できそうなものはありましたか?
ご紹介したすべての方法を、同時に実践するのは難しくても、1つ意識することはできると思います。
ぜひ、みなさんの傾聴力を高める助けになれば嬉しく思います。
さて、当メディアサイトを運営している日本コミュニケーション能力認定協会では、今回ご紹介した傾聴力を高めるトレーニング方法以外にも、対人コミュニケーションの能力向上を目的とした講座の運営も行っています。
具体的には以下のような内容です。
- 1対1での基本的なコミュニケーションスキル
- 周囲に影響をもたらすコミュニケーション
- 信頼関係を構築するための基礎内容
周囲から協力を得て、仕事で成果を上げている人や、プライベートで良い人間関係を築けている人は、こういったコミュニケーションのポイントを身につけています。
人生において、仕事や日常生活問わず、人間関係はずっと続いていきます。
そのため、コミュニケーションを学ぶことは、今後の人生の役立つこと間違いありません。
ご自身を成長させようとお考えの方は、下記のリンクから無料eBOOKをご覧になるか、コミュニケーション能力認定講座へお越しください。
【eBOOK】今なら無料プレゼント
人間関係が劇的に変わる
コミュニケーション
『5つの秘訣』とは?
人間関係や仕事でうまくいく人と、そうでない人の
コミュニケーションには、どのような違いがあるのでしょうか?
この無料eBOOKは、両者の違いを探求して見出した、
コミュニケーションがうまくいっている人たちの
「共通点」や「秘訣」の一部をまとめたものです。
- 部下やチームをもっとうまくまとめたい
- 営業や接客・販売の成績をもっと上げたい
- 人を巻き込む力・人を動かす影響力を身につけたい
- 言いたいことが伝わらずに悔しい思いをしている
- 家族や恋人との関係をもっと良くしたい
1つでも当てはまることがある場合は、
このeBOOKがきっとお役に立てることでしょう。
今すぐ下記からダウンロードして、ご活用ください。