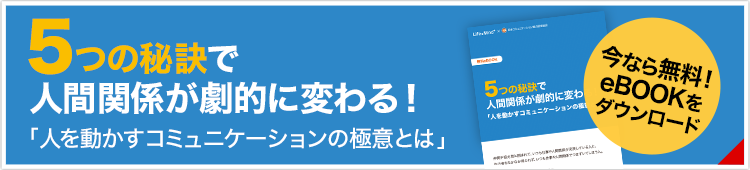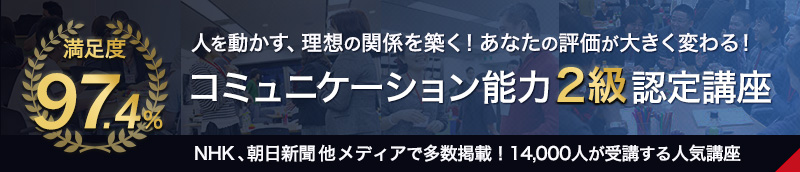あなたが身につけるべきリーダーシップは?基本的な種類とその特徴

ビジネスの世界でよく耳にする機会がある
「リーダーシップ」について、
何となくわかるけど
実際に何をすればいいのか分からない
という人も決して少なくないと思います。
働き方改革により
働きやすくなった反面で、
生産性を向上させないと
成果を上げにくくなった現在では、
リーダーシップの重要性は
更に高まっています。
この記事では
「リーダーシップ」とは何か、
どのようにすれば
発揮することができるのかを
ご紹介していきます。
1.リーダーシップとは?

リーダーシップ(leadership)とは、一般的に「組織内で他者を指導し、目標達成に導いていくための能力」を指します。
わかりやすく言い換えると、「組織として向かうべきゴールを決め、そこに向かい組織を円滑に導く能力」です。
そして、その理論は多義にわたり、時代や環境に合わせて変化をしています。
現在、リーダーシップ能力は、リーダーの役職を持つ人だけではなく、メンバー1人ひとりが発揮していくことが求められる、万人に必須となる能力となっています。
1-1.マネジメントとの違い
よくリーダーシップとマネジメントは混同してしまっていることがあります。
リーダーシップを取っているつもりでも、実はマネジメントで部下の教育や管理をしていたということもよくあります。
違いはいくつかありますが、マネジメントは組織を管理し、部下の育成や指導等を行い、
リーダーシップは人を巻き込んでいき、組織を目標に向かって導いていく影響力である点が大きな違いです。
また、マネジメントは組織を管理する立場の人に求められる能力となりますが、
リーダーシップは組織に属しているメンバーが一人ひとりが発揮することができるのです。
1-2.リーダーシップの代表的な理論3選
リーダーシップの理論は数多く存在しますが、その中から有名なものを3つ紹介します。
- (1)PM理論
- (2)ドラッカーのリーダーシップ論
- (3)コンセプト理論
それぞれについて詳しく説明をしていきます。
1-2-1.日本で最も知られている「PM理論」とは
1960年代に社会心理学者の三隅二不二氏が提唱した理論で、リーダーシップ行動論の1つです。
リーダーシップに必要とされる要素がP(目標達成能力)とM(集団維持能力)の2つの能力で構成されており、
それらの強弱によって4つのグループに分かれているとする理論です。
まずは「P(目標達成能力)」から見ていきます。
これは成果を上げていくために必要なリーダーシップのことを指し、具体的には以下のような行動が該当します。
- 適切な目標の設定/課題の解決
- 目標達成のための指示や管理をすることで生産性の向上
- ルール遵守のための指導
「M(集団維持能力)」はチームや組織をまとめていき、成果を上げ続けていくために必要なリーダーシップを指します。
具体的には以下のような行動が該当します。
- メンバーのトラブルやメンタルのケア
- 良い環境を作るためのコミュニケーション
- 公平なマネジメント
上記のPとMの強弱によって4つのグループ分けがされていきます。

PM型
PとMのどちらも強いため、高い目標達成能力と集団維持能力を併せ持ったタイプです。
このタイプが組織ではもっとも理想的なリーダー像とされています。
PM型のリーダーのもとで働くメンバーは、適正な目標と的確な指示で働きやすい環境で成果を上げていきやすい傾向があります。
Pm型
Pは強いが、Mが弱いため、高い目標達成能力は持っているが集団維持能力がないタイプです。
このタイプでは短期的な成果は上げやすいですが、長期的なチームワークが継続できない傾向にあります。
Pm型のリーダーは長期的な目標設定や指示などは得意ですが、メンバーへの配慮やケアができていないためメンバーのモチベーションを維持することが難しいです。
pM型
Pが弱いが、Mは強いため、目標達成能力は欠けるが集団維持能力が強いタイプです。
このタイプはチームの関係性はとてもいいですが、成果を上げにくい傾向があります。
pM型のリーダーは和気あいあいとしたアットホームな環境を作ることは得意ですが、
目標達成に必要な計画や指示やマネジメントが得意ではなく、成果をなかなか得にくいです。
pm型
PもMも弱く、目標達成能力も集団維持能力も発揮できていないタイプです。
双方が劣っているため、リーダーとしては未熟であり、組織からもメンバーからも認めてもらいにくい傾向があります。
リーダーとしてリーダーシップを発揮していくにはPとMの能力を向上させていく必要があります。
1-2-2.マネジメントの父「ドラッカーのリーダーシップ論」
「マネジメントの父」とも呼ばれたピーター・ドラッカーのリーダーシップ論についても解説していきます。
ドラッカーのリーダーシップ論では、リーダーシップを使命を全うするための「仕事」と位置づけをしています。
先ほどのPM理論などの一般的なリーダーシップ論では、リーダーシップの定義として「個人が発揮するもの」と考えられていますが、
ドラッカーのリーダーシップ論では「組織のミッションである」となっています。
ここでいうミッションとは、「組織は何のためにその事業を行っていくのか」という企業のビジョンなどに関するものです。
そのため、ドラッカーのリーダーシップ論では、リーダーシップを【ミッションに基づいて正しい意思決定を行うこと】と定義づけをしました。
ドラッカーは、ミッションに基づいて正しい意思決定を行うリーダーを周りに鳴り響く「トランペット」に例えました。
そして、そのようなリーダーは、部下に影響を与え、メンバーの主体性を伸ばしていくと考えられています。
1-2-3.状況に合わせた多種多様な「コンセプト理論」
コンセプト理論とは、1960年代に状況や環境により、行動を変えていくのが優秀なリーダーと考えられる「条件適合理論」を元にして提唱された理論です。
その後、1980年代にジョン・コッターが「変革的リーダーシップ理論」を提唱し、それが現在の代表的なコンセプト理論と言われています。
わかりやすく言うと、コンセプト理論は、ある特定のリーダーシップが適しているというわけではなく、
その時その時の状況によって必要なアプローチは変わっていくという理論です。
コンセプト理論は細かいものを含めると多岐にわたりますが、大きく分類された代表的なリーダーシップを5つご紹介していきます。
変革型リーダーシップ
組織やチームに大きな変革をもたらすためのリーダーシップで、経営の根幹からを見直すことで大きな変革を行っていきます。
カリスマ型リーダーシップ
メンバーや組織から厚い信頼を持ち、強力な影響力があります。
組織を変えるための影響力を持つ一方で、依存されてしまうことや後継者問題などが起こりやすい傾向があります。
EQ型リーダーシップ
メンバーの人間関係や環境に重きを置き、働きやすさやメンバーのモチベーションの維持に焦点をあてたリーダーシップです。
ファシリテーション型リーダーシップ
メンバーの一人ひとりの主体的な行動を大切にし、成長や意欲を上げていくことに焦点をあてたリーダーシップです。
サーバント型リーダーシップ
自分の意見とメンバーの意見の双方を尊重しながら、メンバーをサポートし、信頼関係を築いていくことに焦点を当てたリーダーシップです。
コンセプト理論とはこれらのリーダーシップを状況に合わせて、使い分けていく理論です。
1-3.VUCA時代に合わせた近年のリーダーシップ
VUCA(ブーカ)時代とは、正解のない不確実な時代で予測不能な混乱している状態のことを指します。
年功序列によってリーダーの役割が与えられる風潮は次第に弱まるなか、年齢という物差しだけではなく、
今では能力や特性に応じて、柔軟に個人のパフォーマンスを引き出す必要があります。
そのような時代だからこそ、リーダーとしての個の力だけではなく、チームメンバー1人ひとりのリーダーシップの発揮が必要とされています。
そこで求められているリーダーとメンバーの役割の違いは以下です。
- リーダー:
ビジョンやゴールを共有し、チーム全員のリーダーシップの発揮を促す - メンバー:
ビジョンやゴールに向けて、強みを活かしてリーダーシップを発揮する
この役割が機能することで、メンバー全員がリーダーシップを発揮し、主体性をもって行動する状態になり、
ビジョンやゴールをより達成しやすくなるチームにすることができます。
2.リーダーシップを発揮し成果を出すために必要な要素

リーダーシップの種類や定義についてお伝えをしてきましたが、実際にどのようにすればリーダーシップを発揮することができるのか、この章で詳しくご紹介します。
2-1.目標設定をする
リーダーシップを発揮するためには、目標設定が必要不可欠です。
目標設定をすることで、ゴールはどこか、何に焦点を当てていくべきなのかという方向性を明確にすることができます。
メンバーの前に立つリーダーが、まず明確な目標設定をすることで、チームメンバーも同じ目標に向かって進んでいきます。
そして、メンバー自身も、そのゴールを達成するための目標を設定していくことで、ゴールへの具体的な道筋が定まり、
結果として、より多くの成果を上げることができるようになります。
目標を設定することは、効率的に目標達成をすることや、結果が出しやすくなるためチーム全体のモチベーションの向上にも直結します。
そのため、常に短期的な目標・中長期的な目標を設定するようにしましょう。
2-2.コミュニケーション能力を磨く
リーダーシップを発揮するには、コミュニケーション能力が欠かせない要素となってきます。
コミュニケーション能力を高めると、情報の伝達力も高まっていくため、情報共有や意思疎通にかかる時間を大幅に削減することが可能です。
わかりやすく的確な指示をできるようになったり、部下の伝えたい気持ちを瞬時に察することができたりするようになります。
その他にも、コミュニケーションを通じてチームメンバーの理解を深めていくことで、信頼関係を作っていくことができます。
それにより、悩みを相談しやすくなったり、意見を言いやすくなり、メンバーのモチベーションの向上やより建設的な意見が出やすくなります。
結果として、チーム全体が強固な一枚岩となります。
コミュニケーションの活性化は、そのままチームの活性化につながります。
メンバーが主体的に行動していくことで、メンバーの1人ひとりがリーダーシップを発揮していき、チームが目標を達成する可能性は格段に上がっていきます。
ですから、リーダーがコミュニケーション能力を高めることは、リーダーシップを発揮する上で非常に重要な要素です。
2-3.問題意識を持つ
問題意識とは、何が問題なのかを意識すること。簡単に言うと、「なぜ」「どうすれば」という問いを持つことです。
問題意識を持つことは、改善や改革につながる気づきが多くあります。これはリーダーシップに必須の能力です。
日頃からこの問題意識を持つことで、業務改善ができるだけでなく、トラブルの発生時にも迅速に動くことができるようになります。
たとえば、業務改善の視点でいうと、いつもと同じ業務をするにしても、何も考えずに行ってしまうと、その業務は作業となってしまいます。
このままでは、そこから改善や改革につながる気づきを得ることはできません。多くの場合、リーダーが問題点に気づかなければ、メンバーも気づけないケースがあります。
リーダー自身が率先して問題意識を持ち、発生したトラブルやチーム全体の課題に気づくことができれば、チームが停滞せず、目標達成へのスピードも向上します。
また、リーダーの問題意識をチームに発信することで、メンバーの問題意識を底上げすることにも繋がります。
問題を改善する練習を日頃から積み、課題解決力が磨かれた組織は強力です。
トラブル発生時の課題解決力もリーダーに求められる重要なポイントとなりますので、日頃から「なぜ」「どうすれば」という問題意識を持つようにしていきましょう。
2-4.意思決定の速度を上げる
優秀な組織やチームのリーダーは意思決定の速度が早いという特徴があります。
反対に、成果を残せないチームのリーダーは決断力がなく意思決定が遅いと言われています。
意思決定が遅いリーダーは、決断力が低く、その分、必要以上に考える時間が多くなっている可能性があります。
そのため、行動に移す事自体が遅れてしまう傾向があります。
また、チームメンバーが早く動こうとしていても、リーダーが実行の決断をするまで動けないため、チーム全体の動きが止まってしまう可能性もあります。
意思決定の速度を上げていくには、上記に挙げた「問題意識を持つ」ことと「優先順位をつける癖をつける」ことが大切です。
日頃から問題意識を持つことで課題解決力を鍛えることができ、必要な決断をしやすくなります。
また、優先順位をつける癖をつけることで、緊急時には何を切り捨て何を優先で行うのかを決めやすくなります。
2-5.PDCAサイクルを回していく
PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の順番で循環させていくことを指し、
その頭文字を取ってPDCAサイクルと言われています。
それぞれの項目ごとに解説していきます。
| Plan (計画) |
まずは目標の設定と、どうすればその目標を達成することができるのかを考える |
| Do (実行) |
Planで考えた目標達成するためにすることをひたすら実行をする |
| Check (評価) |
Doで実行をしてみた結果を踏まえて、「成功や失敗の要因は何か」「もっと効果を上げていくにはどうするか」を検証していく |
| Action (改善) |
Checkで確認したことを実際に改善していく |
上記のPDCAサイクルをしっかりと回していくと成果を上げていくことができるようになります。
PDCAサイクルを回していくには数値での情報を取り入れることがポイントです。
数値情報がなければ根拠のないものとなってしまい、可視化することができません。
PDCAのそれぞれに数値情報を取り入れることを意識し、サイクルを回していきましょう。
3.リーダーシップをより深く理解し身につけるために

現在においてリーダーシップはリーダーだけでなく、メンバーの1人ひとりも発揮することが求められます。
メンバーがリーダーシップを発揮しやすい環境を作ることは、リーダーの役割といえます。
そのためには、メンバー1人ひとりと密接な信頼関係を築いていく必要があります。
そして、信頼関係を築いていくために最も重要なのは、「自己重要感を満たす」という意識です。
自己重要感とは、簡単に言うと、誰かから認めてほしいという気持ちです。
人は誰もが自己重要感を満たしたいという欲求が、心の深い部分に存在し、そこを満たせられるようになると、あなたの影響力は更に高まっていきます。
こうした内容を知っているかどうかで、あなたの人間関係や信頼関係は大きく変わります。もちろん、リーダーとして上げる成果の大きさにも影響していきます。
このメディアサイトを運営している日本コミュニケーション能力認定協会では、コミュニケーションに関する講座を運営しています。
この講座では、より詳細なリーダーシップの在り方や自己重要感の満たし方を含め、
コミュニケーションを通し対人スキルを学び、信頼関係を構築していく方法をお伝えしています。
コミュニケーションについてもっと学んでみたい、体験してみたいと思った方や話し方によって信頼関係を構築する方法を知りたいと思った方は下記のリンクから詳細をご覧ください。
また、マネジメントについても詳しく学びたいとお考えでしたら、以下の記事もご参考になるかもしれません。
【eBOOK】今なら無料プレゼント
人間関係が劇的に変わる
コミュニケーション
『5つの秘訣』とは?
人間関係や仕事でうまくいく人と、そうでない人の
コミュニケーションには、どのような違いがあるのでしょうか?
この無料eBOOKは、両者の違いを探求して見出した、
コミュニケーションがうまくいっている人たちの
「共通点」や「秘訣」の一部をまとめたものです。
- 部下やチームをもっとうまくまとめたい
- 営業や接客・販売の成績をもっと上げたい
- 人を巻き込む力・人を動かす影響力を身につけたい
- 言いたいことが伝わらずに悔しい思いをしている
- 家族や恋人との関係をもっと良くしたい
1つでも当てはまることがある場合は、
このeBOOKがきっとお役に立てることでしょう。
今すぐ下記からダウンロードして、ご活用ください。